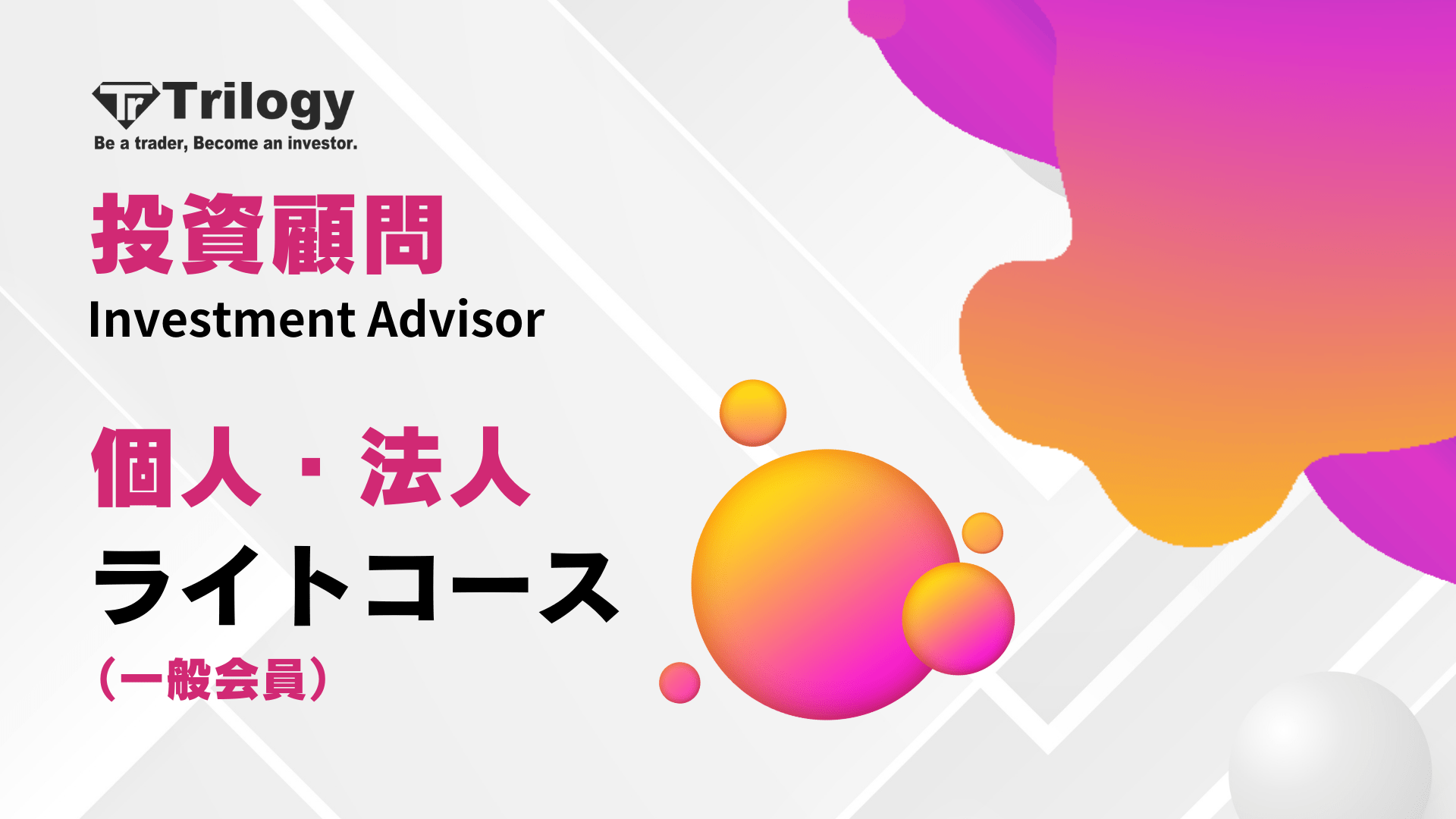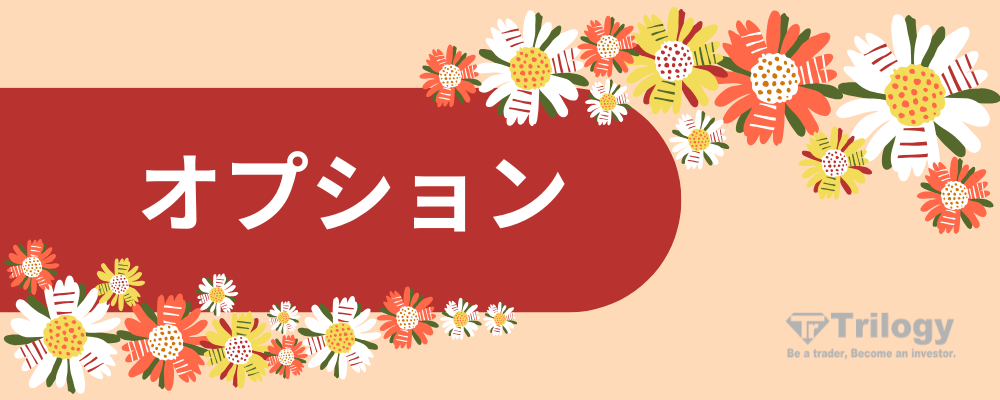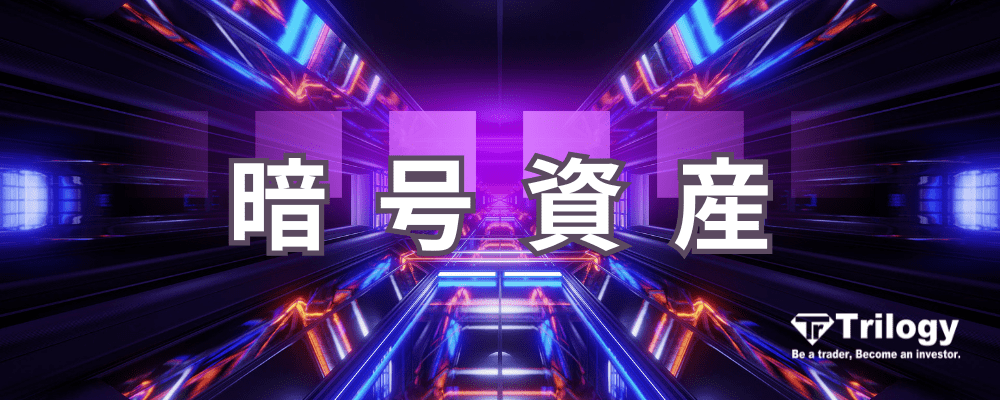日本の資産運用市場が抱える課題

日本の資産運用市場は様々な課題を抱えており、それらの解決に向けた取り組みが進められています。主な課題と解決策について以下に詳しく解説します。
主な課題
- 投資の未活用
- 日本の家計金融資産の半分以上が現預金として保有されており、投資に向かっていない状況があります。これは経済成長や個人の資産形成の機会損失につながっています。
- 低リスク志向
- 日本人は一般的にリスク回避傾向が強く、株式などのリスク資産への投資を避ける傾向があります。これにより、長期的な資産形成の機会を逃している可能性があります。
- 金融リテラシーの不足
- 金融や投資に関する基本的な知識や理解が不足しており、適切な金融判断を下すことが困難な状況にあります。特に「インフレ」「複利」「分散投資」といった基本的な概念の理解が不足しています[2]。
- 世代間・地域間格差
- 若年層と高齢者層、都市部と地方部で金融リテラシーや投資行動に格差があります[2]。
- 資産運用業界の課題
- 日本の資産運用業界は、新規参入が少なく、独自の慣行が海外からの参入障壁となっているなどの課題があります[1]。
解決に向けた取り組み
NISAの拡充と恒久化
個人投資家の参加を促進するため、NISAを抜本的に拡充し恒久化しました。成長投資枠(年間240万円)とつみたて投資枠(年間120万円)を設け、長期・積立・分散投資を推進しています。
金融教育の強化
- 学校教育の充実
- 現行の学習指導要領で金融経済教育の重要性が認識され、その内容が拡充されています。シミュレーションやロールプレイングなどのアクティブ・ラーニングの導入が求められています。
- 生涯学習の推進
- 金融機関、NPO、自治体などが連携し、多様な学習ニーズに対応したプログラムを提供することが重要です。
- デジタル技術の活用
- オンライン学習やマイクロラーニングなど、柔軟な学習形態の導入が進められています。
金融・資産運用特区の創設
金融庁と意欲ある自治体が協働して、特定の地域において金融・資産運用サービスを集積し、高度化と競争力強化を促進する取り組みが進められています。
資産運用業界の改革
- 日本独自のビジネス慣行や参入障壁の是正
- 投資信託の基準価額に係る二重計算の見直しなど、業界の効率化を図っています。
- 新興運用業者の支援
- 新興運用業者促進プログラム(日本版EMP)を通じて、新たな資産運用の手法や技術の開発を支援しています。
アセットオーナーの役割強化
企業年金等のアセットオーナーの役割を強化し、適切な資産運用を促進するための取り組みが行われています。
スチュワードシップ活動の実質化
投資先企業との建設的対話を促進し、企業価値向上と持続的成長を目指す取り組みが進められています。
対外情報発信の強化
日本市場の魅力を国内外に発信し、海外からの投資を呼び込む取り組みが行われています。
まとめ
これらの取り組みを通じて、日本政府は「資産運用立国」の実現を目指しています。個人の資産形成を促進し、国内の投資を活性化させ、「成長と分配の好循環」を実現することが期待されています[5]。
これらの施策の成功には、政府、金融機関、教育機関、そして国民一人一人の協力が不可欠です。長期的な視点で取り組みを続けることで、日本の資産運用市場の課題解決と、国民のファイナンシャル・ウェルビーイングの向上が期待されます。